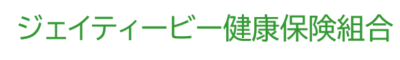![]()
健康保険Q&A
・在宅勤務を実施しているため、回答までに時間を要する場合があります。予めご了承ください。
・メールにてお問い合わせの際、個人情報が記載された届出、申請書等の添付はご遠慮ください。
被扶養者について
※事業主とは、所属会社・所属団体(出向中の場合は出向元会社・団体)を表します。
メールで健康保険組合への直接の提出はできません。「扶養家族増届」に限らず、各種届については、事業主経由で健康保険組合に提出してください。出向者は出向元の事業主経由でお願いします。
> 被扶養者が増えたとき
> 扶養家族増届の様式
「扶養家族増届」に限らず、各種届についての事業所名称欄については、各事業主が記入しますので、空欄のまま事業主経由で健康保険組合へ提出をお願いします。
メールによる申請手続きはできませんので、申請書類を事業主経由で健康保険組合へ提出してください。健康保険証発行に必要となる期間は、申請後10日前後を目安としてください。書類に不備がありますと、健康保険証の発行に時間を要します。予めご了承ください。
> 被扶養者が増えたとき
> 扶養家族増届の様式
勉学に集中・アルバイト不可が被扶養者継続の条件です。「被扶養者継続承認願」と高校卒業証書写を事業主経由で健康保険組合へ提出してください。詳細は健康保険組合ホームページの「被扶養者認定基準」をご覧ください。
> 被扶養者認定基準
主な被扶養者の認定条件としては、①主として被保険者の収入により生活をしていること ②年間収入見込みが130万未満であること(60歳以上及び障害年金の受給要件に該当する場合は180万円未満)となっています。
基本の提出書類は①「健康保険扶養家族増届」、②「住民票原本(世帯全員分続柄記載あり)」、③「課税・非課税証明書(原本)」、④現在、認定対象者が加入している「健康保険証の写し」を事業主経由で提出となっていますが、必要書類については状況によりが異なるため、健康保険組合ホームページの「被扶養者認定基準」をご覧ください。
> 被扶養者認定基準
POSITIVEと健康保険の手続きは連動していないため、「健康保険扶養家族増届」等を事業主経由(健康保険組合への直送は厳禁)で健康保険組合へ提出してください。健康保険組合ホームページの「被扶養者認定基準」をご覧ください。
> 被扶養者認定基準
夫婦に収入がある場合、年間収入の多い方の扶養とすることとなっていますが、扶養申請の希望を伺い、健康保険組合で扶養認定の審査を行います。希望どおりの認定が出来ない場合があります。ご了承ください。
> 被扶養者認定基準
健康保険証について
→㈱JTB所属の方は、札幌のSBC(送付先住所はJ-web【㈱JTB社員向け】各種申請方法・必要書類一覧に記載)へ送付
→関連会社所属の方は、総務担当へ
② 喪失証明書発行依頼
→直接健康保険組合へ郵送またはFAXでお送りください。
例)東京都品川区東品川2-3-11 → 東京都品川区東品川二丁目3番地11号
病気・けがをしたときの給付について
ご申請される場合は、申請書一覧より、No.212「限度額適用認定申請書」をご記入の上、健康保険組合へ郵送にてご提出ください。
なお、オンライン資格確認が利用できる場合は限度額適用認定証の申請は不要です。
※食事代・差額ベッド代は対象外
申請書はJTB健康保険組合ホームページ 各種手続き申請書 – 申請書一覧の No.212「限度額適用認定申請書」を印刷してください。
ご申請の際は必要事項をご記入の上、健康保険組合へ郵送にてご提出ください。
※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の支払いが免除されます。健康保険組合へ限度額適用認定証の手続きは必要ありません。マイナ保険証を利用しましょう!
>マイナ保険証の詳細はこちら
再度、申請が必要となります。申請書一覧より、No.212「限度額適用認定申請書」をご記入の上、健康保険組合へ郵送にてご提出ください。
また、有効期限の切れた限度額適用認定証はすみやかに健康保険組合に返却してください。
> 申請書一覧
被保険者期間内の被扶養者については「健康保険限度額適用認定証」も有効期限内なので、利用可能です。
なお、ご使用が終わりましたら、すみやかに健康保険組合へ送付にて返却ください。
診療月から3~4ヵ月を目安に還付いたします。在職中の方は、事業主(所属会社)経由で還付いたします。
任意継続保険にご加入の方は、任意継続保険加入時にご指定いただいている口座へ振り込みます。
支払時に支払決定通知書をお送りいたしますので、金額等はそちらでご確認いただけます。
※再発行は行っておりませんので、大切に保管してください。
まずは以前加入されていた健康保険組合に医療費の返金をしてください。ご返金手続き終了後、以下の書類をJTB健康保険組合にご提出ください。
①療養費支給申請書(国内用)
②診療報酬明細書 原本
③領収書 原本
> 申請書一覧
支給可否については、健保組合にて審査を行った上で決定いたしますので事前に、お電話等で支給可否をお答えすることはできません。
申請書一覧より、№206「傷病手当金請求書」を印刷してください。
①被保険者記入欄を記入する
②医療機関にて「保険医の意見」を証明してもらう。
③事業主(所属会社の人事・総務)へ送付する。
その後、事業主(所属会社)から健保組合へ送付されます。
> 申請書一覧
再度、申請が必要となります。「健康保険限度額適用認定申請書」を健康保険組合へお送りください。また、有効期限8月末の「健康保険限度額適用認定証」の使用が終わりましたら、すみやかに健康保険組合へ送付にて返却ください。
> 申請書一覧
なお、オンライン資格確認が利用できる場合は限度額適用認定証の申請は不要です。
手続きなしで高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要となります。
なお、申請期間(労務不能期間)に在職期間中が含まれている場合は、在職時と同様に事業主(所属会社)の証明が必要となります。
給付関連手続き*については、POSITIVEと連携していないため、POSITIVEからの申請はできません。
*療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、限度額適用認定証の申請 等出産・育児について
以下を参照ください。
> 出産したとき
※産休、育休の保険料免除の手続きは事業主(所属会社の人事・総務)が行いますので、被保険者からの健保組合への申請は不要です。申請書一覧より、「出産手当金請求書」を印刷してください。
①ご本人記入欄を記入する
②出産された医療機関にて、医師の証明欄を記入してもらう
③事業主(所属会社の人事・総務)へ提出する
その後、事業主(所属会社)から健保組合へ送付されます。
> 申請書一覧
出産後のご申請となります。
> 出産したとき
出産手当金請求書はご本人記入欄と医師の証明欄を記入後に、事業主宛に請求書のご提出をお願いします。提出先については、事業主にご確認お願いします。また、出産手当金は産前産後休業中に給与が出ないか、減額されている方が対象となりますので、対象となるかどうかについても事業主に併せてご確認ください。また、健康保険組合への申請についてはPOSITIVEと連動していないため、健康保険に関するPOSITIVE申請は不要です。
> 出産手当金の申請
出産後の申請となります。出産後に医師または助産師より出生証明を受けた後、事業主経由にて健康保険組合へ申請をお願いします。
> 出産手当金の申請
亡くなられたときについて
被保険者が死亡した場合、生計を共にしていた家族に対して埋葬料として5万円が支給されます。
生計を共にしていた家族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に対し5万円を限度とし、葬儀にかかった実費を埋葬費として支給します。
※参列者へ接待費用、飲食代は含みません。
> 亡くなったとき
退職と任意継続について
申請手続き方については、以下を参照してください。
資格喪失日(退職日の翌日)から申請可能です。申請期限は、資格喪失日から20日以内に当健康保険組合必着です。
在職中より扶養家族に入っている被扶養者は、引き続き、任意継続被保険者の被扶養者となります。また、任意継続被保険者としての加入期間は、最長2年間となりますので、2年を過ぎましたら国民健康保険への切り替え手続きが必要です。
比較ポイントは以下のとおりです。
①保険料について
任意継続被保険者資格の取得による保険料は、事業主負担分がなくなり、保険料の全額が、ご本人の自己負担となります。(40歳以上65歳未満の方は介護保険料も全額自己負担)保険料は、退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けて算出された金額の全額がご本人の自己負担となります。また保険料率は毎年3月(4月納付分)に改定されます。
※標準報酬月額は給与明細等に記載されている場合があります。直近の給与明細等をご確認ください。
> 保険料額表
②任意継続保険料は扶養家族の人数によって変動しません。
国民健康保険料については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
③当組合独自の付加給付制度や健診制度があります。
国民健康保険については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
新しい健康保険証交付後、下記書類を当健康保険組合まで送付してください。
①当健康保険組合加入の事業所に就職する場合
・任意継続保険の健康保険証(扶養家族分も含む)、高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
・メモで「〇日から〇会社に就職」とお知らせください。
②当健康保険組合加入の事業所以外に就職する場合
・「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」
・任意継続保険の健康保険証(扶養家族分も含む)、高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
・就職先の健康保険証写し(健康保険の資格取得年月日が記載された頁)
喪失月以降の保険料を納付いただいている場合は還付となります。
該当の方に健康保険証等受領後、「保険料還付請求書」を送付します。
> 申請書一覧
令和4年1月1日施行の健康保険法改正にて、自己都合での脱退が認められるようになりました。
① 資格喪失(脱退)希望の旨を、当健康保険組合の所定用紙「任意継続被保険者資格喪失申出書」へ記入後に郵送にてお申し出ください。
② ①が届いた日の属する月の翌月1日を持って任意継続被保険者資格は喪失となりますので、資格喪失後、当健康保険組合が発行する「健康保険資格喪失証明書」をもって、次に加入する国民健康保険(または家族の被扶養者)へ切り替え手続きを行うことになります*。
(喪失日以降に保険証は使用できません。使用された場合は、後日医療費の返還請求を致します。)
③ 喪失日(翌月1日)以降速やかに当健康保険証を健康保険組合に返却してください。
*ただし、ご家族の被扶養者として健康保険の資格取得の認定については、申請先の健康保険組合の判断になりますので、まずは申請先のご家族の健康保険組合にお問い合わせください。仮にご家族の健康保険組合で被扶養者の認定がされなかったとしても、当健康保険組合の任意継続被保険者に戻ることはできません。その場合は、国民健康保険に加入することになります。
任意継続保険に加入すると保険証記号・番号が変わるため、ご使用いただけません。再度、「健康保険限度額適用認定証」の申請をしていただく必要があります。ご退職後、「任意継続保険資格取得申請書」とともに、「健康保険限度額適用認定申請書」、現在お持ちの「健康保険限度額適用認定証」を当健康保険組合へお送りください。
> 申請書一覧
各種健診について
ハピルス健診からのログインにより、予約完了の最終画面に表示される料金が、正当な自己負担額となります。
> 人間ドック
窓口でお支払いいただいた金額は、健康保険組合の補助金を差し引いた自己負担分の金額となっています。
> 人間ドック
受診できる医療機関は、「女性社員婦人がん検診」をご確認ください。「検診実施医療機関一覧表」に掲載されている医療機関のみにて受診可能となります。
医療機関への直接申込みはできません。「けんしんナビ」からの予約をいただき受診ください。
自己負担額は、受診後に業務委託先となる一般財団法人日本健康文化振興会よりお申込み時に登録したメールアドレスへメールが送信されますので、内容をご確認の上お支払いください。なお、追加した検査項目の料金は全額自己負担となりますので、受診当日に医療機関の窓口で精算してください。
その他
なお、当健康保険組合は2023年1月受診分より閲覧可能ですが、それ以前は閲覧できません。
KOSMO Communication Web にてユーザー登録が完了している場合、ログイン画面でID/PWを入力→通知情報照会→医療費照会→医療費照会画面で年月を選択(表示されているのは最新の月)し検索ボタンを押す→選択した月の医療費が確認できます。
KOSMO Communication Web にてユーザー登録が完了していない場合、初期登録用Webサービスのご案内(ハガキ)をお手元に用意してKOSMO Communication Web のログイン画面より登録完了してください。その後、再度ログイン画面よりご覧ください。
KOSMO Communication Webより印刷した医療費通知は確定申告の「医療費控除の明細書」としてご利用になれます。
(念のため、お手元の領収書等と付け合せをしてください)
確定申告に利用可能な医療費通知は12月上旬に掲載する「当年9月診療分」までとなります。
当年10月~12月診療分の医療費通知がダウンロードができる時期は次のとおりです。
【10月診療分】 翌年1月上旬
【11月診療分】 翌年2月上旬
【12月診療分】 翌年3月上旬
確定申告の際に医療費通知が添付できない期間については、国税庁ホームページより「医療費控除の明細書(PDF)」をダウンロードし、領収書等に基づいて「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付してください。
なお、この場合には当該医療機関の領収書を確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
「医療費通知」に掲載の金額等の情報は、医療機関から健康保険組合への請求に基づいて作成されています。医療費通知と領収書の金額等に相違がある場合は医療機関にご確認ください。